皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
長女の誕生日です!
4人の子供達から
日々勉強させていただいております。
弊社では、
お客様が収集いただいた資料については、
郵送でお送りいただいております。
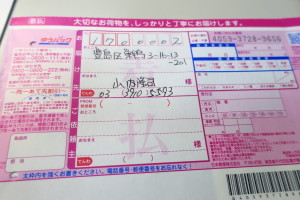
■本日は、
「健康保険、厚生年金、雇用保険の加入について」です。
数年前から、
建設業許可申請では、
「健康保険、厚生年金、雇用保険の加入の有無」についての
現状確認が求められております。
現時点(平成28年6月)では、
未加入の状態でも
建設業許可の取得は可能です。
■法律上、
法人は、
「健康保険、厚生年金の加入」が義務付けられております。
また、
従業員を雇用した場合には、
「雇用保険の加入」が義務付けられております。
■「健康保険、厚生年金、雇用保険」を加入する場合に
多くのお客様から下記の点について
ご質問をいただきます。
A)手続きはどのように進めればよいですか?
B)何に気をつければよいですか?
■下記に、
ご説明させていただきます。
A)手続きはどのように進めればよいですか?
⇒従業員10名前後であれば、
手続きは自社で行ってよろしいと思います。
「会社の実印」と「ゴム印」を持参して、
関係窓口に行ってみてください。
最初から「専門家」に依頼することは
必要ないと思います。
まず、
ご自身で進めてみて、
「これはちょっと大変だ」と
感じることが多く出てきた段階で、
「専門家に依頼すること」を
選択肢としてあげてください。
建設業許可は自社で行うことは
まず無理ですが、
今回の手続きは自社でもできます。
弊社では、
何か必要な手続きがあると、
「会社実印」と「ゴム印」を持参して
自社で申請をしております。
わからないことは、
窓口の方が丁寧に教えてくれます。
B)何に気をつければよいですか?
⇒「健康保険と厚生年金」については、
給料と比例して税額が変動します。
そのため、
「単に手続きをすればよい」という視点に加えて、
「キャッシュアウト」のインパクトを
考慮する必要があります。
具体的に言うと、
「年収600万円」と「年収2000万円」では
保険料に違いがあります。
税金の支払いは、
会社における「どの支払いよりも優先」されます。
※支払いがおくれると延滞税も発生します。
そのため、
支払額がどの程度になるかを
あらかじめ想定しておくことが必要です。
今回のような視点を持たずに、
「専門家」に任せてしまうと、
「キャッシュアウト」の説明なしに
手続きだけが進み、
支払いに追われる相談者が多数いらっしゃいます。
支払いの金額については、
役所の窓口に問い合わせていただいてもわかります。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します。