皆さま、こんにちは。
代表の山内隆司(やまうち たかし)です。
本日は、
早朝から受付完了した新規申請の申請内容について
審査官と電話協議を進めさせていただきました。
弊社のように
創業から37年以上も建設業許可申請専門で行っておりますと、
審査官から逆に質問を受けることが多いです。
「創業37年」「建設業許可専門」「誠実」に
業務を行わせていただいている結果だと思い、
これからも真剣に業務を進めさせていただくことを
改めて決心いたしました。
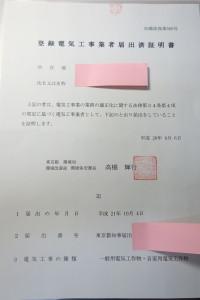
■本日は、
「電気工事業者に必要な許認可の種類について」です。
電気工事業を営む場合には、
大きく分けて下記の2つの許認可申請が必要になります。
1)電気工事業者登録
2)建設業許可(電気工事業)
■上記2つの許認可の違いを
ご説明させていただきます。
1)電気工事業者登録
⇒工事現場で直接電気工事を行う場合。
2)建設業許可(電気工事業)
⇒500万円以上の工事の受注をする場合。
※最近の実際の現場では、
500万円という金額は重視しておらず、
建設業許可の有無を求められているようです。
■どちらの許認可も
「有資格者」がいないと申請できません。
他の建設業許可の場合のように、
「実務経験だけ」で取得をすることができないので、
有資格者の確保が重要になります。
代表的な資格は、
下記の4種類です。
A)第1種電気工事士
B)第2種電気工事士
C)1級電気施工管理技士
D)2級電気施工管理技士
■上記の4種類のいずれかの有資格者がいれば
すべて順調に進むというかというと、
気をつけなければいけない点があります。
1)電気工事業者登録をする場合
⇒第1種電気工事士
⇒第2種電気工事士
免許交付日以降に
電気工事業者登録をしている会社での実務経験3年が必要
2)建設業許可(電気工事業)を取得する場合(2種類あります)
⇒一般建設業許可の場合
A)第1種電気工事士
B)第2種電気工事士
※免許交付後の実務経験3年が必要
C)1級電気施工管理技士
D)2級電気施工管理技士
⇒特定建設業許可の場合
C)1級電気施工管理技士
■上記のように、
いろいろな組み合わせとなりますので、
人材確保については、
中長期的視野で取り込んでいく必要がございます。
以上です。
ご参考になれば幸いです。
※※創業から37年(代表行政書士の実務経験は22年以上)気を付けていることがあります。※※
1.「説明はわかりやすく」
2.「説明は短く」
3.「説明は難しい言葉は使用しない」
創業50年にむけてこれからも、
多くの方のお役に立てるように頑張ります!
※本ブログの著作権は発行者に帰属し、
無断転載することを禁止します。